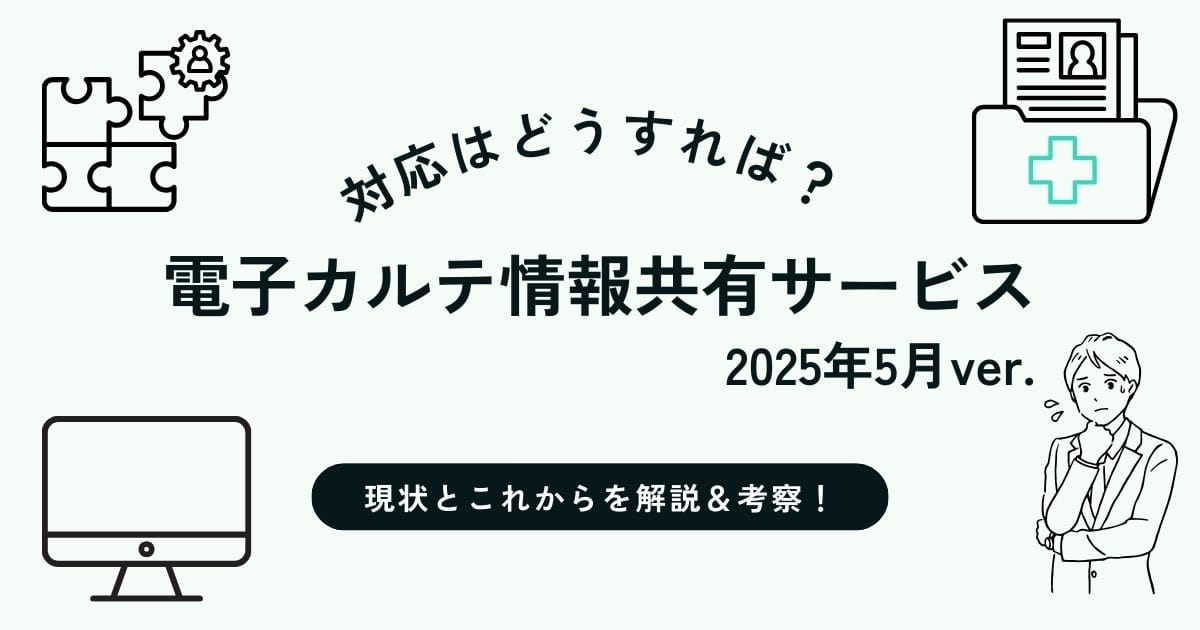医療DXの中核として国が推進する「電子カルテ情報共有サービス」。
ただ現状が不透明であり、「実際にどこまで進んでいるのか分からない」「自院は何をすればいいのか不安」ということはありませんか?
特に2024年度から新設された「医療DX推進整備加算」との関係もあり、導入や対応を急ぐべきか判断に迷う医療機関も少なくないのではないでしょうか。
また、制度導入のスケジュールや補助金の活用、電子カルテの標準化対応など、多くの悩みがあるかと思います。
本記事では、電子カルテ情報共有サービスの基本から、2025年以降の導入スケジュール、直面する課題、そして医療機関が今すぐ取り組むべき実践的な対応までを、予測や考察も交えながら、現場目線でわかりやすく解説します。
焦らず、確実に制度に対応していくための判断材料として、ぜひ最後までご覧ください。
電子カルテ情報共有サービスとは?
電子カルテ情報共有サービスとは、全国の医療機関や薬局が、患者の診療情報を安全かつ効率的に共有するために国が整備を進めるシステムです。
このサービスは、政府が推進する「全国医療情報プラットフォーム」の中核を担っており、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)政策の柱のひとつとされています。
本サービスでは、医療機関が保有する診療記録、検査結果、処方歴などを、患者の同意のもとで安全にやりとりできるようになります。
これにより、紹介状の紛失や重複検査といった課題を解消し、医療の質の向上や業務の効率化が期待されます。
主な3つの機能
- 紹介状送付サービス
医療機関が作成した診療情報提供書や退院時サマリーを、オンライン資格確認ネットワーク経由で他の医療機関に送信できます。 - 6情報閲覧サービス
傷病名、アレルギー、薬剤禁忌、感染症、検査、処方の6つの情報を、患者のマイナンバーカードによる同意のもと、全国の医療機関で閲覧可能にします。 - 健診文書閲覧サービス
特定健診や人間ドックなどの健診結果を、医療機関や保険者、患者自身がオンライン上で確認できます。
利用者別のメリット
| 利用者 | 主なメリット |
|---|---|
| 患者さん | 紹介状の持参不要、重複検査の削減、緊急時のスムーズな対応、健康管理の質向上 |
| 医療機関 | 診療引き継ぎの迅速化、事務負担軽減、診療の精度向上、紙書類の管理負担軽減 |
| 保険者 | 健診データの即時入手、保健指導の質向上、医療費の適正化、費用対効果の分析促進 |
現在の進捗と導入スケジュール
2025年1月よりモデル事業が全国10地域で開始されましたが、現時点で本格運用には至っておらず、テストマーケティング段階が継続中です。
下記は現在でている今後の進行スケジュールになります。
現在出ている予定(2025年以降)
| 時期 | 内容 |
| 2025年1月 | 全国10地域でモデル事業スタート(中核病院・周辺医療機関による検証) |
| 2025年3月 | 標準型電子カルテα版(診療所向け)提供 第1弾 |
| 2025年夏頃 | 標準型電子カルテα版 第2弾提供予定 |
| 2025年10月 | 診療報酬での加算評価(技術評価・補助金適用含む) |
| 2026年3月 | モデル事業完了見込み、本格運用の体制整備へ |
| 2027年度 | 標準型電子カルテの本格提供予定 |
執筆は2025年の5月ですので明らかな遅れている状況です。
ではなぜ遅れているのかその要因を考えます。
導入遅延の要因
- 電子カルテの普及率不足:診療所・中小病院では導入率が依然として低水準。
- ベンダー間の対応進捗の格差:標準化(HL7 FHIR対応)へのスピードに差があり、特に地方ベンダーに課題が残る。
- 補助金制度の不確実性:明確な指針や申請スキームが整っておらず、意思決定に影響。
- 支援人材の不足と地域格差:機器設定や導入支援を担う要員が不足しており、地域間の対応力に差がある。
以上の要因がかんがえられることから、今後の制度普及と本格展開において、以下の2つの課題が大きな障壁であると思われます。
- 電子カルテ未導入施設の山:全体の約半数が依然として電子カルテを導入しておらず、2026年3月の本格運用目標に対して足かせとなっています。政府は標準型電子カルテの無償提供や補助金強化などで対応を模索中という情報もありますが、電子カルテの無償提供については今既に数ある電子カルテ会社さんにとっても、既に導入しているところにとっても大きな不利益と捉えかねません。補助金の可能性はあるかもしれません。
- ベンダー支援体制の山:特に中小ベンダーでHL7 FHIR準拠や保守対応が遅れているケースが見られ、ベンダーさんによっても対応できる力の格差がでてきている現状があります。医療機関側もサポート力を見極めてベンダー選定を行う必要があります。
この2つの山を超えるためには、補助制度の見直し、現場への人的支援、地域単位での連携体制の整備が求められます。
さらには2025年7月と10月がターニングポイントとなっています。
2025年7月と10月は注目の月!
なぜターニングポイントとされるのか理由を解説します。
✅ 1. 政府・厚労省による制度評価と補助金の見直し時期
- 2025年7月は、電子カルテ情報共有サービスや電子処方箋など医療DX関連施策の「中間評価」が予定されている重要な節目です。電子カルテ情報共有サービスは電子処方箋との連動前提で設計されているため、2025年7月時点での電子処方箋の普及度が「連動型加算」の適用条件に直結する可能性も指摘されています。
- 普及状況や現場の声をもとに、診療報酬上の加算や補助金スキームの再設計(再配分)が検討される可能性が高いとされています。
- ここで導入率が芳しくない場合は、加算や導入支援策の強化(あるいは統合・延期)が行われる可能性も。
✅ 2. 2025年10月:診療報酬の技術的評価の反映時期
- 2025年10月からは、電子カルテ情報共有サービスに関する診療報酬の加算評価が反映される予定です(点数の明記や要件整備が進行中)。
- 現場の導入・運用状況を踏まえて、加算の適用有無や点数の上下が実施されるため、この時期を境に導入の流れが一気に加速・停滞する可能性があります。
✅ 3. 補助金と技術対応の整備が進む区切り
- 10月をめどに主要ベンダーのHL7 FHIR対応(標準化)も概ね整うと見込まれており、これ以降は導入準備が現実的に進められる医療機関が増加する見通しです。
- 補助金の対象範囲や見積区分も10月以降により具体化されると考えられ、「本格導入の判断ができる時期」とされています。
医療機関が今やっておいた方が良いことは?
以下に、医療機関が今やっておいた方が良い対応事項を整理します。
それぞれの取り組みには、今後の展望に基づく理由があります。
- ベンダーへの確認と仕様チェック
理由:対応が未定のままでは補助金や診療報酬加算のタイミングを逃す可能性があるため。 - 補助金制度の最新情報収集と申請準備
理由:補助金対象が明確化されており、要件を満たせば費用負担を軽減できるため。 - 今後の診療計画に基づいた導入判断
理由:今後引退・譲渡を見据えるなら、無理に導入せず待機戦略もありうるため。 - 対応可能なベンダーの比較検討
理由:導入後のサポート体制や費用構造が中長期的な満足度に直結するため。 - 情報共有とスタッフ教育の準備
理由:現場運用での混乱を防ぎ、スムーズな導入初期対応を実現するため。
優先度は?
| 優先度 | 項目 | 内容概要 |
| 高 | ベンダーへの確認 | 対応可否・時期・補助金対応などの確認 |
| 高 | 補助金情報と見積作成 | 補助金適用を前提に、導入・改修の費用確認 |
| 中 | ベンダーの比較 | 実績、支援力、クラウド対応などの総合比較 |
| 中 | スタッフ教育と業務フロー準備 | 患者説明、運用マニュアル、掲示物作成などの整備 |
| 低 | 診療方針・将来設計に基づいた導入判断 | 引退・承継予定の時期に応じた柔軟な判断 |
【2025年版】電子カルテ情報共有サービスとは?現状と医療機関が今すべき対応を徹底解説まとめ
- 電子カルテ情報共有サービスは、紹介状や健診結果、6情報などを全国の医療機関で共有可能にする中核システム。
- 現在はモデル事業段階にあり、2026年3月までの本格運用を目指して整備中。2025年7月・10月が判断の分岐点。
- 普及には「電子カルテ未導入施設の対応」と「ベンダー選定の目利き力」が鍵となる2つの山。
- 医療機関は補助金の活用、ベンダー選定、院内体制整備などを早期に進め、制度変化への対応力を高める必要がある。
これからの1年は、制度の方向性と医療機関の準備状況が整うかどうかを占う極めて重要な時期です。
焦って導入を進めるのではなく、補助金の活用タイミングや診療報酬の評価制度をしっかりと見極め、無理のないスケジュールで導入・対応を進めていくことが成功の鍵となります。
少しでも参考になれば幸いです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。